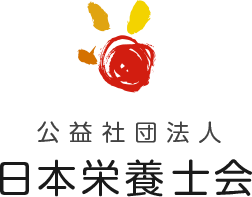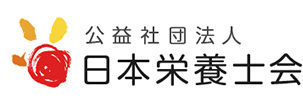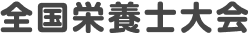各種制度・指針・調査・文献検索
公的機関の情報を中心に、各種制度・ガイドライン・統計調査結果・文献検索などの情報サイトをジャンル別に紹 介します。
食事摂取基準

国民の健康の保持・増進、生活習慣病の予防のために参照するエネルギー・栄養素の摂取量の基準を示したものです。性・年齢階級別に、1日の摂取量で示され、5年ごとに改定されています。
情報発信元:厚生労働省
健康づくり対策

健康日本21の内容、その分析評価を行う事業などが示されています。健康日本21(第三次)は、誰一人取り残さない健康づくりの展開(Inclusion)とより実効性をもつ取組の推進(Implementation)を通じ、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための国の基本方針で、令和6(2024)年から10年間に達成すべき数値目標を設定しています。
情報発信元:厚生労働省

「健康な食事」とは何かを明らかにするための検討会の報告書(平成26(2014)年)。人々の生活の営みや環境、背景にある食文化まで、栄養学や医学の専門家、食に関わる多領域の専門家や実務者により、幅広い視点から検討されています。
情報発信元:厚生労働省

健康日本21(第三次)における休養・睡眠分野の取組を推進するため、生活指導の実施者(保健師、管理栄養士、医師等)、政策立案者(健康増進部門、まちづくり部門等)、職場管理者、その他健康・医療・介護分野において良質な睡眠の確保を支援する関係者等を対象者として、睡眠に係る推奨事項や参考情報をまとめています。
情報発信元:厚生労働省

近年の生活習慣病の有病者・予備群が増加している状況を改善するため、平成20(2008)年4月より実施されている制度で、国民に向けて本制度の活用を勧めています。メタボリックシンドロームの概念を取り入れ、リスクの数により保健指導を3段階で行うのが特徴です。
情報発信元:厚生労働省

特定健診・特定保健指導を効果的に実施するために、医師、保健師、管理栄養士等が参考すべきプログラムの令和6(2024)年度版。具体的なプログラムの例のほか、基本的な考え方や実施の留意点等がまとめられています。
情報発信元:厚生労働省

「自然に健康になれる持続可能な食環境づくりの推進に向けた検討会」報告書(2021年6月公表)や東京栄養サミット2021における日本政府コミットメントを踏まえ、産学官等連携による推進体制として、「健康的で持続可能な食環境戦略イニシアチブ」を立ち上げました。
情報発信元:厚生労働省

食育基本法の制定、「健康日本 21 (第二次)」の開始、食育基本法に基づく第3次食育推進基本計画などが作成されましたが、食生活に関するこれらの幅広い分野での動きを踏まえ、平成28(2016)年に改定されました。
情報発信元:農林水産省

健康で豊かな食生活の実現を目的に、食生活指針(平成12(2000)年)を実際の行動に結びつけるものとして、平成17(2005)年に策定されました。1日に何を、どれだけ食べたらよいかを、「コマ」を用いて、料理単位で例示しています。
情報発信元:農林水産省

食育に対する国民の意識を把握し、今後の食育推進施策の参考とするために実施されている調査の報告書。平成17(2005)年以降、ほぼ毎年行われています。
情報発信元:農林水産省

食育の普及・推進を目的とした、できるところから始めるためのガイド(平成24(2012)年)。乳幼児から高齢者まで生涯にわたり、世代に応じた具体的な食育の取り組みが示されています。(平成31年3月改訂)
情報発信元:農林水産省

令和3~7(2021~2025)年度に実施する食育推進基本計画。第1次計画(平成18~22(2006~2010)年)、第2次計画(平成23~27(2011~2015)年)、第3次計画(平成28~令和2(2016~2020)年)を経て、国民の健康や食を取り巻く環境の変化、社会のデジタル化など、食育をめぐる状況を踏まえ推進しています。
情報発信元:農林水産省

食育推進基本計画、健康日本21における栄養・食生活分野等の目標項目に関する各種事業等の取り組みデータベース。効果的な取り組みを共有し、相互に利活用することにより、食育等の推進に役立てることを目的にしています。
情報発信元:国立健康・栄養研究所

昭和22~平成14(1944~2002)年までの国民栄養調査の結果が示されています。「国民健康・栄養調査」の結果は、当時は「国民栄養の現状」という名称で公表されていました。
情報発信元:国立健康・栄養研究所

国民の身体の状況、栄養・食品摂取量、生活習慣の状況等についての調査結果が示されています。国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料となる調査で、昭和22(1944)年から毎年実施されています。
情報発信元:厚生労働省
公衆衛生関連統計

わが国の全ての人と世帯を対象とする、人口、世帯状況、就業状況などについての最も重要な統計調査。得られた統計結果は、国や地方自治体をはじめ、民間企業や研究機関で広く利用され、国民生活に役立てられています。5年ごとに実施されています。
情報発信元:総務省

わが国の出生、死亡、婚姻、離婚、死産などの人口動態事象を示しています。人口および厚生労働行政施策の基礎資料を得ることを目的とする調査で、明治32(1899)年に開始され、毎年実施されています。
情報発信元:厚生労働省

平均寿命、平均余命を表したものです。保健福祉の水準を総合的に示す指標となっています。国勢調査時に集計される完全生命表と、それ以外の年に毎年集計される簡易生命表があります。
情報発信元:厚生労働省

地域住民の健康の保持・増進を目的とした保健施策の展開等についての報告書。国や地方自治体の地域保健施策のための基礎資料を得ることを目的に、毎年作成されています。
情報発信元:厚生労働省

保健、医療、福祉、年金、所得等の国民生活の基礎的事項を示しています。世帯員を対象に、毎年実施されています。厚生労働行政の企画・運営に必要な基礎資料を得ること、各種調査の調査客体を抽出するための親標本を設定することを目的としています。
情報発信元:厚生労働省

給食施設数、管理栄養士・栄養士数など、各都道府県、指定都市・中核市における衛生行政の実態を示しています。衛生行政運営の基礎資料を得ることを目的に、毎年実施する調査です。
情報発信元:厚生労働省

平成25(2013)年度開始の健康日本21(第二次)の推進にあたって定められた、「地域における行政栄養士による健康づくり及び栄養・食生活の改善について」と「その基本指針」が示されています。
情報発信元:厚生労働省
家計

国民生活における家計収支の実態(収入・支出、貯蓄・負債など)が示されています。国の経済政策・社会政策の立案のための基礎資料を提供することを目的に、全国約9千世帯の人びとを対象に、毎月調査しています。
情報発信元:総務省

世帯を対象に、購入頻度が少ない高額商品・サービスの消費やICT関連消費の実態が示されています。毎月実施され、調査結果は、個人消費動向の分析、景気動向の把握のための基礎資料として利用されています。
情報発信元:総務省

家計の収入・支出、貯蓄・負債、耐久消費財、住宅・宅地などの家計資産について示されています。家計の構造を所得、消費、資産の3つの側面から総合的に把握することを目的に、5年ごとに実施する調査です。
情報発信元:総務省
栄養指導・栄養教育

平成17(2005)年4月に開始された栄養教諭制度、およびその免許制度について示したものです。栄養教諭は、学校における食育推進の指導体制の要として、重要な役割を担っています。
情報発信元:文部科学省
母子栄養

乳幼児の栄養方法、食事の状況等の実態が示されています。母乳育児の推進や乳幼児の食生活の指導のための基礎資料を得ることを目的とする調査で、10年周期で行われています。
情報発信元:厚生労働省

乳幼児の身体発育の状態を示しています。乳幼児の身体発育値、発育曲線を明らかにして、乳幼児保健指導の改善に資することを目的とする調査で、10年周期で行われています。
情報発信元:厚生労働省

健やか親子の内容や関連情報を示しています。健やか親子21は、全ての子どもが健やかに育つ社会の実現を目指し、関係するすべての人々、関連機関・団体が一体となって取り組む国民運動です。
情報発信元:こども家庭庁

「食を通じた子どもの健全育成のあり方に関する検討会」の報告書(平成16(2004)年)。家庭や社会の中で、子ども一人ひとりの「食べる力」を豊かに育むための支援づくりの必要性を強調しています。
情報発信元:厚生労働省

妊娠、出産、授乳等に当たっては、妊娠前からの健康なからだづくりや適切な食習慣の形成が重要であるため、妊娠前からの健康づくりや妊産婦に必要とされる食事内容とともに、妊産婦の生活全般、からだや心の健康にも配慮した、10項目から構成されています。
情報発信元:こども家庭庁

授乳及び離乳の望ましい支援の在り方について、妊産婦や子どもに関わる保健医療従事者を対象に、所属する施設や専門領域が異なっても、基本的事項を共有し一貫した支援を進めるために作成されました(2007年3月)。2019年3月改定。
情報発信元:厚生労働省
臨床栄養

日本医薬情報センター(JAPIC)が提供する国内外の医薬品情報に関するデータベースポータル。無料のデータベースを集約した「iyakuSearch」と、これに有料データベースを含めた「iyakuSearch Plus」があります。
情報発信元:日本医薬情報センター

日本医薬情報センターにより公開されているデータベース。添付文書、文献、学会、規制、治験、の各段階における医薬品情報を簡単に検索できます。
情報発信元:日本医薬情報センター

医薬品の研究開発力で高い評価を得ているMerck & Co., Inc., Kenilworth, N.J., U.S.Aが提供しているデジタル医学事典です。
情報発信元:MSD

医学中央雑誌刊行会が発行する国内最大級の医学文献情報のデータベース。インターネットでの配信サービス「医中誌Web」にて情報を提供しています。
情報発信元:特定非営利活動法人医学中央雑誌刊行会

日本透析医学会が毎年発行している「図説わが国の慢性透析療法の現況」に掲載された医療データ。データの利用には、同学会が定める「統計資料」利用規定を順守する同意が必要です。
情報発信元:日本透析医学会
高齢者栄養・介護・福祉

介護保険事業の実施状況を示しています。今後の介護保険制度の円滑な運営に資するための基礎資料を得ることを目的とした調査の報告書で、毎年調査・作成されています。
情報発信元:厚生労働省

全国の介護サービスの提供体制、提供内容等を示しています。介護サービスの提供面に着目した基盤整備に関する基礎資料を得ることを目的に行われる調査で、毎年実施されています。
情報発信元:厚生労働省

従前の二次予防事業の内容を踏まえつつ、平成26年介護保険法改正後の内容に即した見直しや、運動器の機能向上・栄養改善・口腔機能向上等のプログラムにおける最新の知見等の観点から、見直しをしています。
情報発信元:厚生労働省

2001年にWHO総会で採択された、人間の生活機能と障害の分類法を示しています。それまでのマイナス面を分類するという考えに対し、ICFは生活機能というプラス面から見るように視点を転換し、環境因子の観点も加味されました。
情報発信元:厚生労働省
食品の成分・表示

食品の安全性、一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会を確保するため、これまでの食品衛生法、JAS法、健康増進法の食品の表示に関する規定を統合した法令(食品表示法、平成25(2013)年)と、関連情報を示しています。
情報発信元:消費者庁

食品表示制度についての情報をまとめています。食品表示について、食品表示法等(法令および一元化情報)、機能性表示食品に関する情報、健康や栄養に関する表示、安全や衛生に関する表示、品質等選択に役立つ表示の制度について、などが示されています。
情報発信元:消費者庁

「トランス脂肪酸の情報開示に関する指針」(平成23(2011)年)により、適切な食品選択のため、トランス脂肪酸を含む栄養成分に関する情報が、食品の容器包装、事業者のホームページ、新聞広告等を通じて広く開示されるようになりました。
情報発信元:消費者庁

常用食品の標準的な成分値を、1食品1標準成分値として、可食部100g当たりの数値で示しています。最新の2020年版(八訂)は、2,478 食品を収載しています。別に、アミノ酸成分表編、脂肪酸成分表編、炭水化物成分表編があります。
情報発信元:文部科学省
食品衛生・安全

食中毒の患者および死者の発生状況を的確に把握し、発生状況を解明することを目的とした調査。原因となった場所、発生年月日、原因食品、病因物質、患者数、死者数などについて、毎年調査されています。
情報発信元:厚生労働省

衛生的な食肉等の提供のため、と畜場で行われる毎月の検査を家畜生産段階にフィードバックし、生産段階での対策を促進すること、都道府県等の衛生行政推進にあたって全国的な状況等を随時利用できる体制を構築することを目的に、毎年実施している調査です。
情報発信元:厚生労働省
給食管理

給食における食中毒予防のために、HACCPの考えに基づいた、大量調理施設、中規模調理施設等における衛生管理マニュアル。「大規模食中毒対策等について」(平成25(2013)年最終改正)の別添として示されました。
情報発信元:厚生労働省

平成16年公表の「保育所における食育に関する指針」の普及を図り、その活用法を促進させるためのガイドライン(平成24年)。保育所での食事提供のあり方や事例を示しています。
情報発信元:こども家庭庁

学校給食の現状と課題を把握し、その改善充実に資することを目的に、毎年実施されている調査。調査事項は、学校給食実施状況、学校給食費、米飯給食実施状況、学校給食における食堂・食器具使用状況です。
情報発信元:文部科学省

学校給食における栄養内容等の実態を把握し、食事内容の充実を図ることを目的に、毎年実施されている調査。調査事項は、栄養素等摂取状況、使用食品の分類別摂取状況です。
情報発信元:文部科学省

学校給食の実施の適正を期するために定められた基準。実施の対象、実施回数、食物の栄養内容、給食施設・設備、学校給食摂取基準について示しています。2020年2月一部改正。
情報発信元:文部科学省

学校給食における食中毒予防のための基準(平成21(2009)年)。HACCPの考え方に基づき、給食現場の施設・設備等の実態把握に努め、衛生管理上問題のある場合には、学校医または学校薬剤師の協力を得て、速やかに改善措置を図ることになっています。
情報発信元:文部科学省
その他文献検索

学協会の情報発信機能を支援するために、科学技術振興機構(JST)が構築した、科学技術情報発信・流通統合システム。平成28(2016)年1月現在、約1,900誌の約2,712,000記事を収載しています。
※「日本栄養士会雑誌」に掲載された実践事例報告は、こちらに掲載されています。
情報発信元:国立研究開発法人 科学技術振興機構

国立保健医療科学院が運営するデータベース。厚生労働科学研究の研究成果を広く国民に情報公開するために、各種の研究報告書の概要版および報告書本文をデータベース化しています。
情報発信元:厚生労働省

継続的に更新される栄養学の知識データベースであり、エビデンスに基づく実践ガイダンスへの簡単なアクセスを登録会員(有料)へ提供するシステムです。
カナダ栄養士会によって始められたもので、現在は、オーストラリア、ニュージーランド、イギリス、アメリカで活用されています。
情報発信元:カナダ栄養士会