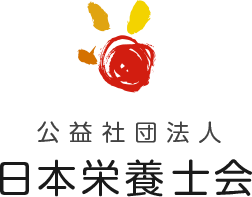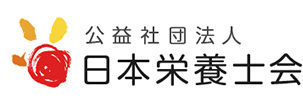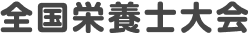"小さい町"だからできる、「今よりもっと幸せに子育てできる町」を目指す子育て支援
2025/03/03
トップランナーたちの仕事の中身#101
安原美香さん(福井県高浜町こども未来課・こども家庭センターkurumu、管理栄養士)

管理栄養士として「高浜町のこども家庭センターkurumu」で子育て支援に取り組む安原美香さん。2019年のグッドデザイン賞を受賞する等、全国的に注目を集める、小さい町の特性を生かした利用者目線に立った食を通した子育て支援について伺いました。
小さい町の特性を生かした「kurumu」の誕生
福井県の最西端に位置する高浜町は豊かな自然に囲まれた風光明媚な町として知られています。安原美香さんは、高浜町役場で初めて、正規職員の管理栄養士として24年前に入職しました。
「高浜町は宿泊客でにぎわう観光地でしたが、20年ほど前から日帰り客が主流となりました。現在の人口は約9,600人、年間の出生数は近年60~70人と少子高齢化が進んでいます。高校卒業後に進学や就職で町を離れる若い世代が多いのも特徴です」と安原さん。
少子化対策、子育て支援事業のあり方を話し合う中生まれたのが、"小さな町"であることを強みに変えるという逆転の発想でした。「住民同士が顔見知りになりやすく、声を掛け合えるという、大都会にはない特性を活用して町ぐるみの子育て支援を目指しました。こどもの健やかな成長だけでなく、親たちの心身の健康サポートを積極的に展開し、高浜町の理念である『今よりもっと幸せに子育てできる町』を実感できる取り組みを目指したい。子育てのしやすさが住みやすさにつながり、高浜町で長く暮らすようになってほしいという願いもありました」
同時期に高浜町の機構改革が始まったことも、事業展開の後押しにつながりました。
「2007年に母子保健と児童虐待対応担当を一課にし、子育て支援事業に着手しました。しかし、2016年ごろには深刻な相談や要保護児童の増加等からハイリスクケースへの対応で手いっぱいになり、住民全体への支援が十分できない状況でした。問題解決に向けた動きと、2017年の『母子保健法』の改正、地方自治体における『子育て世代包括支援センター』の設置が努力義務になったことが重なり、2018年に高浜町保健福祉センター内に『子育て世代包括支援センターkurumu』を設置しました。『kurumu』(くるむ)とは、全てのこどもが温かい愛情に包まれ、子育て中の家族を優しく支える。そしてぬくもりに包まれた人が次は誰かを包む人になるという高浜町の理念を込め、『包(くる)む』、『赤ちゃんのおくるみ』をイメージして名付けたものです」
その後、コロナ禍での育児不安の増加・虐待の深刻化を受け、2023年に保健、福祉、医療費助成業務等の子育て支援部門を「こども未来課」として統合し、高浜町保健福祉センター内に設置しました。同時に「子育て世代包括支援センターkurumu」は「こども家庭センターkurumu(以下、kurumu)」と名前を変え、子育て支援に係る窓口を一本化したことで、妊娠期から子育て期まで切れ目のない相談・支援がより充実しました。安原さんは管理栄養士として母子保健部門の食育・栄養相談の業務を担っています。

「kurumuを始動するにあたって住民のニーズや問題点を分析したところ、『出産までに親になる準備が整わない』、『産後、子育てのスタートで幸せを感じられない』、『生後5カ月以降は人や社会とのつながりと充実感が持てていない』ことが分かりました。これをもとに事業の見直しを行いました」
具体的な取り組みを紹介します。取材でkurumuに伺うと、1階フロアの真ん中に設置された広々としたプレイルームが目に飛び込んできました。「kurumu立ち上げの第一歩として、木製の大きな遊具のような小さな路地のような作りに改修しました。ほどよく区切られた空間が解放感とプライベート感の両方を保ち親子同士の交流を生みます。年間利用者は1万人にのぼります。職員が施設内を移動する際は必ずプレイルームを通るので、利用者と自然と声をかけ合う機会も増えます」
産後ケアや五感を使う食体験で、こどもも家庭も笑顔に
「2019年に始めた旅館での産後ケアに加え、2020年には、1歳までのこどもと家族が参加できるスマイルマルシェも産後ケアに位置付けました。スマイルマルシェでは、離乳食等の相談、家族のボディーケアやリフレッシュ、そして、赤ちゃんの発達等を促すケアや遊びのメニューがあり、自由に参加できます」年間約200組の親子が参加し、父親の参加も増えてきているといいます。
「多くの自治体では、産後ケアは育児不安や保健指導が必要な人が対象ですが、町では当初から全ての親子を対象にしています。事業を通して、参加者同士や地域とのつながり、そして、kurumuとのつながりも深まり、不安の軽減や充実感のある子育てにつながっていると感じています」
発達に合わせて変化していく食事は成長の喜びを実感できる反面、テキストどおりに進まない等悩みや不安を抱えることも多くみられます。「大切にしているのは一緒に作る・作るところを見る・みんなで食べる等の時間を通して、音や匂い、触感等の五感を活用した食体験を取り入れることです」
取材の日は10カ月健診に合わせて離乳食後期のライブキッチンと試食が開かれていました。「調理デモでは家族の食事からの取り分けメニューを中心に、発達に合わせた味付けや形状等のポイントを紹介します。手軽に作れることを実感してもらったあとは、試食をしながら相談に応じます。食べる様子を親と一緒に見ることで、成長の確認や内容のステップアップ等が具体的になり、自信を持って離乳食を進めてもらえる機会になっています。また、みんなで一緒に食べることで、赤ちゃんは刺激し合い、親同士も情報交換の場になる等、共食の効果も感じます」
初期、中期にも同様の講座を開いているといいます。また、1歳から参加できる収穫や調理体験を交えた食育講座も好評を得ています。
「わくわく☆ちびっこ食体験クラブは、1~3歳のこどもが親子で敷地内の菜園で野菜を収穫したり、料理したりして味わうというものです。自分で作ったごはんは味もうれしさも格別のようでみんなパクパク。この講座をきっかけに家庭菜園や親子調理を始めましたという声も多く届きます。また、日頃、菜園の手入れをしてくださるセンターの管理人さん等、地域の皆さんとの交流も生まれ、親子でおいしいものを楽しみながら人とのつながりが生まれる食育にもなっていると思います」

家族、地域にさらに広がる支援
安原さんは離乳食や幼児期のこどもや家族以外にも、積極的に支援の輪を広げています。スマイルマルシェでは産後ケアだけでなく、妊娠中の家族の講座も同時開催しており、健やかな妊娠、出産、子育てに向けた栄養講話をしています。
また、18歳のためのクッキングでは高浜町を離れて1 人暮らし等をしても役立つ自炊術やメニューの選び方、町オリジナルの健康づくり10か条をはじめ、将来の健康に役立つ栄養講話を行っています。
「入職以来、離乳食相談等で会った親子の皆さんはよく覚えています。お母さんが『離乳食を食べてくれない』と悩んでいたお子さんが18歳の講座に参加したり、親として再会したりすることも増え、すてきに成長した姿に会えると本当にうれしく、行政管理栄養士冥利に尽きます」
最近kurumuでは父親支援について模索している中で、お父さんたちから「妊娠中や子育てに役立つ料理が知りたい」という声があがり、お父さんクッキングをスタートしました。
「これからも高浜町の特性を生かしながら、食や健康づくりを通して人とのつながりが広がって、日々の食が充実するとともに、この町で子育てできて幸せ、住んで幸せと住民の皆さんの笑顔『スマイル』が増えていく取り組みを行っていきたいと思います」
プロフィール:
2000年神戸学院大学栄養学部栄養学科卒業。2001年福井県高浜町に入職。京都府栄養士会所属。