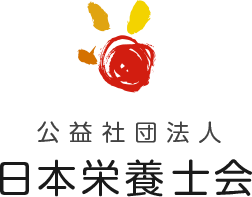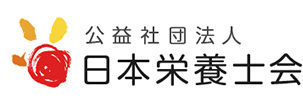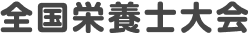重症心身障害児が生涯を安全安心に過ごせる、デイサービス事業所運営に取り組む
2025/04/04
トップランナーたちの仕事の中身#102
大高美和さん(NPO法人ゆめのめ理事長、管理栄養士)

左:娘の芽彩さん 右:大高美和さん
娘の芽彩(めい)さんが重症心身障害を持って誕生したことをきっかけに病院管理栄養士を辞め、福祉の世界に飛び込んだ大高美和さん。医療的ケア児や重症心身障害児のデイサービス施設の運営を通して障害児の永続的な居場所作りを目指す活動について伺いました。
障害のある娘の誕生をきっかけに福祉の世界に飛び込む
管理栄養士の大高美和さんは、2018年に「NPO法人ゆめのめ」を立ち上げ、現在、理事長として重症心身障害児および医療的ケア児を対象にしたデイサービス事業所を東京都日野市で2施設運営しています。
「きっかけは娘の芽彩がさまざまな障害を持って生まれたことでした。当時、私は急性期、精神科、療養型病院の管理栄養士として10年ほど勤務しており、主に高齢者の嚥下調整食を担当していたにも関わらず、摂食嚥下障害のある娘にどんな離乳食を作って良いのか分かりませんでした。
離乳食の本を参考に作ってもなかなか食べてもらえないストレスと仕事で疲れていたこともあり、ミキサーにかけたみそ汁ごはん、納豆ごはんを作るのが精いっぱい。試行錯誤を続けていたある日、定期健診で娘が貧血と診断されました。管理栄養士なのに娘を貧血にしてしまったショックは大きかったです」
その後、芽彩さんは自宅近くの保育所に入所し、昼食は保育所でミキサーにかけた給食になりましたが、保育所には専門スタッフがおらず、適切な食事介助やケアは得られませんでした。ちょうどその頃、地元の障害児サークルに参加した際に、他市でデイサービス事業を行う会社が、日野市にも施設を設立したいが、管理者がいないという話を聞きました。大高さんは家族に相談することなく、その場で「やります」と自ら手を上げました。自分は病院を辞めることになるが、障害があってもこどもらしく、友達と一緒にのびのびと過ごせる居場所作りに関わりたいという思いが勝ったからだといいます。
「娘は保育所と併用してデイサービスに通うことにしました。看護師、理学療法士といった専門スタッフによるケアが充実した環境で預けられ、本当にホッとしました。一方で私にとっては、児童福祉施設の施設長を管理栄養士が務めていることが珍しかったため取材を受けるようになり、日本摂食嚥下リハビリテーション学会学術大会のパネルディスカッションに参加する機会を得ることにつながりました。こうした出来事のおかげで多職種の専門家と知り合うことができ、これまで疑問だったことや重症心身障害児における食事の重要性を学ぶきっかけとなりました」
重症心身障害児のためのデイサービス事業所を設立

しかし、施設長を務めて2年経つ頃から運営会社の経営が悪化、大高さんをはじめスタッフへの給料が支払われなくなりました。大高さんは退所し、ほどなくデイサービスは閉所されました。
「施設長を2年務めるうち、安全安心な居場所が必要な障害を持つこどもがたくさんいることを実感し、自分で理想の居場所を作ろうと決意しました。重症心身障害児の場合、摂食嚥下障害があるケースが多く、食事は栄養を摂取することが優先されがちですが、母、管理栄養士として、障害があっても食事を楽しむ経験を重ねてほしいと考え、食事に重点を置いた施設作りを目指しました」
そこで、2018年にNPO法人ゆめのめを立ち上げ、2019年に重症児対象・多機能型児童発達支援・放課後等デイサービス事業所、デイケアルームフローラ(以下、フローラ)を設立。フローラの対象年齢が0~18歳で特別支援学校卒業後に、週5日通える居場所がないことをなんとかしたいという思いから、2022年には東京都で前例のない19歳~成人も対象にした重症児者対象・多機能型放課後等デイサービス・生活介護事業所である日野坂キャンパス(以下、日野坂)を設立しました。
「どちらの施設にも看護師が常駐しており、療育的支援や医療的ケアが行える他、保護者の負担を少しでも軽くするために入浴サービスを行っています。食事は給食、おやつを施設内で手作りして提供しており、食べる力に合わせて硬さを調節して刻むかミキサーにかけています。食事介助はスタッフ1人でこども数人を担当することが一般的ですが、フローラと日野坂では、重症児対象の特例で手厚い人員配置が可能となり、マンツーマンで介助を行うことで安全性を確保しています」
乳幼児の摂食嚥下障害に適した離乳食とは
乳幼児が通うフローラでは、かつて大高さんが悩んだ離乳食も提供しています。
「フローラの保護者ばかりでなく、摂食嚥下障害のある乳幼児を持ち、離乳食で悩んでいる保護者はとても多いです。理由の1つに、障害があると発達がゆっくりになるため、離乳食の進め方が月齢を基準にしている一般的な離乳食の本では、自分のこどもにはどの月齢を参考にすれば良いのか分からないことがあります。また、摂食嚥下障害があると口腔機能の課題に合わせた食形態にしなければなりませんが、本に記載されている固さや大きさの調理だけでは不十分なことがあります」と大高さん。さらに、よく誤解されるのが乳幼児と高齢者は同じ嚥下調整食で良いのではないかという点です。
「私も芽彩の離乳食で悩んでいたときは、高齢者とこれから発達を獲得していく小児は違うのではないかと思いましたが正解が分かりませんでした。しかし、専門知識を学んだことで乳幼児は成長段階であり、食べる経験が口腔機能等の発達につながることを知りました」
現在、大高さんが参考にしているのが日本摂食嚥下リハビリテーション学会作成による『発達期摂食嚥下障害児(者)のための嚥下調整食分類2018』であり、舌の押しつぶし運動を促すような形態等、摂食嚥下機能の発達と獲得を促しながら、安全に食べることを配慮した食形態がまとめられています。
「管理栄養士・栄養士でも乳幼児の摂食嚥下障害を知らない人は多いですし、理論を知っていても調理の仕方を指導できる人は限られています。制度としても、乳幼児、小児の摂食嚥下障害の栄養指導の支援等は遅れているのが現状です」
今年、大高さんはこれまでフローラの保護者に向けた離乳食教室で紹介してきたレシピをまとめた本を出版予定です。「少しでも摂食嚥下障害の離乳食作りに悩んでいる保護者の役に立ち、社会の理解を深める一歩となればうれしいです」
楽しみながら五感や身体機能の発達を促す

大高さんは食育にも力を入れています。取材で訪れた日、フローラと日野坂ではこどもたちが参加しておやつの蒸しパン、クッキー作りをしていました。
「材料の卵を触って感触を確かめる、電動ミキサーで材料を混ぜるといった作業では、五感が刺激されるとともに、普段動かすことの少ない手の運動にもなります。好きな作業のときはうれしい、苦手なときはちょっと嫌といった感情表現の機会にもなっています」
この他、ダンスインストラクターである保護者が指導にあたり、座ったり寝転んだりした状態で手や足を音楽に合わせて動かすダンス教室や、専門家による家庭でできる科学実験等、月に10種類ほどの特別教室が開催されています。
「こうした教室が開催できるのはスタッフの協力があってこそです。現在、利用者は両施設で68人、スタッフは41人となり、医師、歯科医、歯科衛生士に嘱託をお願いする大所帯となっています。福祉の仕事は、『人のために役立つことだから処遇は我慢して』といった考えでは、良いスタッフを確保し、運営していくことはできません。今後は重症心身障害児に対する理解者を増や
していき、利用者の親なき後まで見すえた生涯にわたる居場所にしていくためにもスタッフを大事にして進んでいきたいと思います」
プロフィール:
2005年女子栄養大学栄養学部卒業後、管理栄養士として病院に就職。2018年にNPO法人ゆめのめを設立し、重症心身障害児のデイサービスを行う施設を運営する。東京都栄養士会所属。