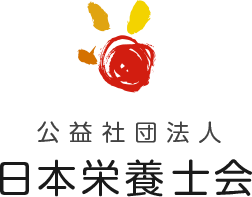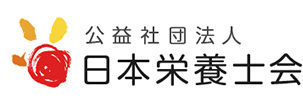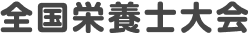徹底したマニュアルの活用で理想の管理栄養士育成を目指す
2025/06/02
トップランナーたちの仕事の中身#104
堤 亮介さん(平成医療福祉グループ、管理栄養士)
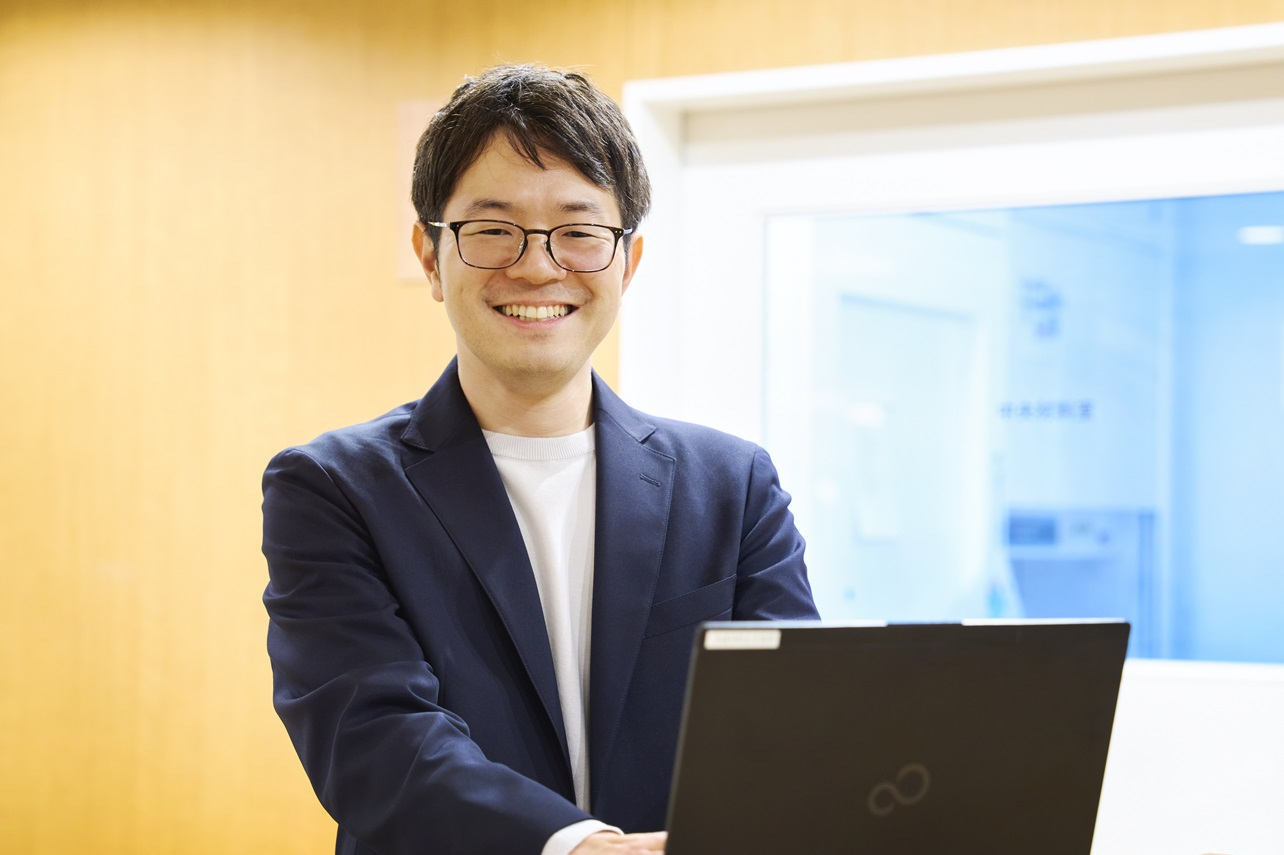
大手医療福祉グループでグループ全体の管理栄養士業務の整備と統括を担う堤亮介さん。大グループに求められる栄養管理の標準化、社会人教育といった組織の業務改善にマニュアルを活用し、成果を上げる取り組みについて伺いました。
刺激となった栄養ケア・マネジメント
管理栄養士の堤亮介さんは、神奈川県立保健福祉大学を卒業後、平成医療福祉グループ(以下、グループ)に入職し、現在、栄養本部部長を務めています。
「グループは全国に100以上の病院、介護施設、福祉施設等を運営しており、回復期から慢性期の患者や高齢者に医療福祉サービスを提供しています。グループ全体で、栄養部には1,587人、このうち管理栄養士は275人が在籍しており、その統括を担当しています」と堤さん。
入職後、最初の仕事は介護老人福祉施設の栄養管理業務でした。グループでは、全ての施設が直営給食でグループ内統一献立を実施しているため献立作成業務はありませんでしたが、食材管理、調理師への指導、調理補助等、現場で必要なスキルを身に付けました。近隣施設への異動を含め約5年間、管理栄養士として順調に歩んでいましたが、どこかにこのままでいいのかという思いがあったといいます。
堤さんは学び直しの必要を感じ、グループの許可を得て施設での仕事を続けながら母校の神奈川県立保健福祉大学の実践教育センターで栄養ケア・マネジメント課程を学びはじめました。栄養ケア・マネジメント課程は、人間栄養学に基づいた栄養の知識、技術およびマネジメント能力を習得し、栄養ケア・マネジメントにおいてリーダーシップを発揮できるエキスパートの育成が目的です。
「もともと何かを企画し、運営方法を考えることが好きなこともあり、まさに自分にはまった分野に出合え、大きな刺激になりました」
マニュアルと管理栄養士キャリアラダー
2015年、堤さんに転機が訪れました。課程修了に際して行ったグループ上長への内容報告が評価され、施設勤務と兼任でグループ本部の栄養本部勤務の配属が決まり、2018年には栄養本部専任になりました。
「栄養本部は組織的な業務改善が求められる中、そのかじ取りを担うために 2013年に立ち上げられました。栄養業務支援課、企画業務課、調理業務支援課、教育学術課、ロジスティクス課の5つに分かれ、現場の管理栄養士が安定して働けるよう増員や待遇の整備・改善、現場のマニュアルの整備や献立の作成支援、食材の管理体制の整備等に取り組んでいます」
とりわけ徹底しているのが 2015年から取り組んでいるマニュアルの整備です。ポータルサイトには細分化された数百ものマニュアルが集められ、職員はアクセスすれば必要な情報がいつでも手に入ります。例えば栄養管理と給食管理であれば、栄養管理プロセス、栄養アセスメント、ミールラウンド、大量調理、調理補助、献立表の理解、患者や入所者家族への接し方といった具合です。
「2021年の介護報酬改定で栄養マネジメント強化加算が新設された際は、運用に関するマニュアルを早急に作成し、改定直後の4月から各施設で算定することができました。こうしたタイミングを逃さないスピード感も重要だと考えています」
近年は、作成するマニュアルが変化しているといいます。「グループとして大事にしているのが、職員教育の重要性です。経済産業省が提唱する社会人基礎力という考え方を導入し、誰もが新人時代に必要な基礎教育から管理栄養士として活躍し、キャリアを昇華するのに必要なマニュアルを作成し、それを用いた管理栄養士キャリアラダーを整備しました」
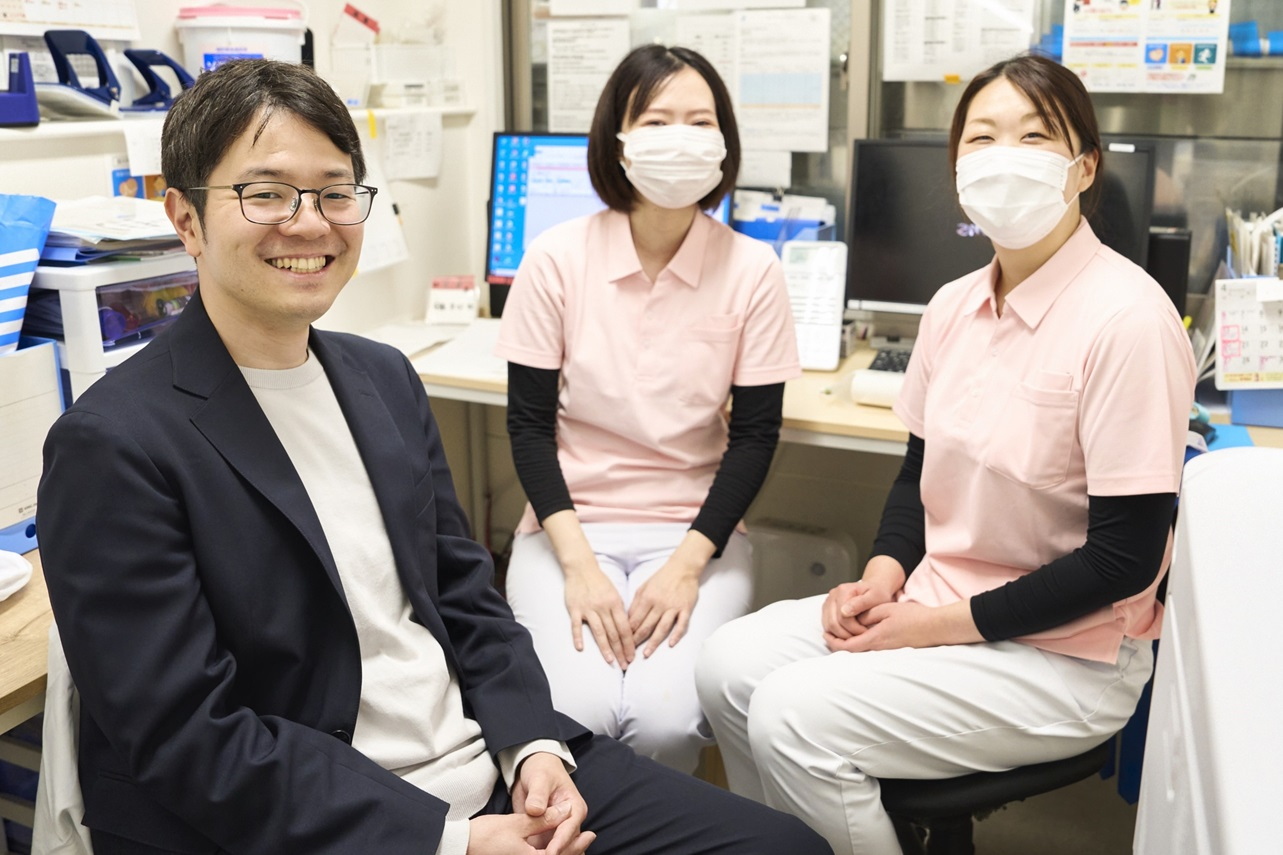
こうした支援体制の整備に着手した背景の1つには、「管理栄養士の発信力の弱さの改善」があると堤さんは指摘します。
「管理栄養士一人ひとりはより良い栄養管理業務について考えているのに、他職種や利用者に十分伝えられていません。これは社会人として他者とのコミュニケーションの取り方、伝える力の不足が原因だと考えます」
また一方で、部下への指導の仕方が分からないという役職者が増えていること、管理栄養士が単独配置から複数配置になっても、後輩管理栄養士への指導ができないため、実質的に二馬力になっていない等の問題も起きているといいます。そのため、社会人基礎力マニュアルでは問題点と、改善策として言葉のかけ方や対応策を具体的に記すことで、自分に当てはまるケースを探しやすく、すぐに役立てられるように工夫しています。また近年、栄養学は医療、福祉の現場でも注目されており、医学部において栄養教育の導入が検討されるようになりました。
「栄養ケアの重要性が他職種に認識されるのはうれしいことです。しかし、管理栄養士一人ひとりが専門職としてできることを明確にしておかなければ、いずれ管理栄養士の存在意義がなくなりかねません。マニュアルを活用することで、管理栄養士の立場の向上、役職者の育成につなげていきたいと思います」
利用者の要望に徹底的に寄り添う
取材に訪れた日は、新入職員に向けたオンライン研修会が開かれていました。会場には常菜食、軟菜食(嚥下調整食 4)、ソフト食(嚥下調整食 3)、ペースト食(嚥下調整食 2-2)の献立が展示され、調理師から調理ポイントの説明があり、その後、堤さんから栄養部の仕事についての講演が行われました。

「私は管理栄養士の 1人として医療、福祉の現場では栄養なくして治療もリハビリも効果が出ないと考えています。当グループでは、最後まで口から食べることを諦めず、患者が食べたいと思えるおいしい食事の提供をポリシーに掲げています。その一例が、2015年から実施している年間365日異なる食事の提供です。こうしたことの実践には、他職種との連携が欠かせないことを入職時から理解してほしいと思い、研修会には調理師に参加してもらい、私の講演では施設で働く全ての職種の業務内容を必ず説明します」
どうしても口から食べられない利用者には経管栄養としてグループで開発・製造する半固形の天然濃厚流動食(以下、PEGペースト)を提供します。
「入院患者や入所者は、自宅に戻ると栄養管理が難しく、体調を崩すケースが多々あります。市販の流動食は粉末の栄養素を調合して作ったものが多いですが、PEGペーストは肉や魚、野菜といった合計18種類の食材を使用しているので家庭で手作りすることができ、栄養管理を継続しやすいというメリットがあります」
この他、食事が十分に取れない場合や、栄養量が不足している場合の栄養補給のために、食事に付加する栄養補助飲料やゼリー等のオリジナルの付加食を約80種類用意しています。
「最初の一口を気に入ってもらえると、その後の栄養管理がうまくいく傾向があります。そのため、食欲不振に気が付いたときは患者に食べたいものを聞き、付加食にないものは管理栄養士が買いに走ることも珍しくなく、各施設でそのための予算を計上しています。患者の要望にとことん寄り添うことで、必要な栄養と食材、調理法までをつなげるのが管理栄養士に求められる役割だと思います」
堤さんは管理栄養士を目指す学生にも目を向けています。
「当グループにおける実習生の受け入れ、就職説明会を積極的に行い、私自身は管理栄養士養成校でゲストスピーカーとして講演に取り組み、職員・役職者育成のマニュアルをもとに情報発信をしていきたいと考えています。病院、福祉施設に管理栄養士がいることで、利用者のQOLは著しく向上します。管理栄養士キャリアラダーをうまく活用して一人ひとりが理想の管理栄養士に成長できる支援を続け、病床9,000床を利用する患者、利用者のQOL向上に貢献していきたいと思います」
プロフィール:
2012年神奈川県立保健福祉大学卒業後、同年、平成医療福祉グループの介護老人福祉施設ヴィラ南本宿に入職。2015年からは栄養本部の業務を兼任し、施設・病院の厨房立ち上げに携わる。2015年神奈川県立保健福祉大学の実践教育センターで栄養ケア・マネジメント課程修了。管理栄養士。神奈川県栄養士会所属。